| 中国は 1980 年代以降、キャッチアップを目標に、米シリコンバレー型企業成長モデルの導入を、外資誘致と並ぶハイテク政策推進上の重要戦略として位置づけた。その成果はインキュベータ(企業孵化器)の整備、起業の促進などに現れ、一部で“カエル跳び”型進化を達成しつつある。 | |
| 他方、このハイテク企業成長モデルは資本市場整備や中小企業金融制度の遅れ、下請け・外注などに伴う合理的商習慣の未発達などの問題にも直面している。“ステップ・バイ・ステップ”でしか進めない問題もあるということだ。 | |
| しかし、経済発展と科学技術水準の向上などを背景に、中国のハイテク政策は基礎研究に重点を移しつつあり、中国人研究者の論文への注目も高まるなど中国の科学技術は世界水準に向かいつつある。 |

■経済発展に向け技術の産業化に重点
中国の技術開発は「物まね」イメージがまだまだ根強い。いまや世界に冠たる存在になった家電産業にしても、平面大画面テレビ、DVD(デジタル多用途ディスク)、高性能エアコンなど新製品はあらかたが日本をはじめとする技術(および基幹部品)の取り込みによるものだ。
日本の新技術を発売後ただちに「盗む」ために日本に人員を配置しているメーカーもある。製品開発はできても独自技術の研究開発にはまだまだ至らないのが中国のメーカーの実力であり、まして基礎研究面では中国は発展途上国の域を出ていない。
政府の「ハイテク政策」を見ても、 1980 年代から始まったいくつかの技術開発計画は、過去「国情に合わせて」経済発展のための技術の産業化に大きな重点を置いてきた(図表1)。
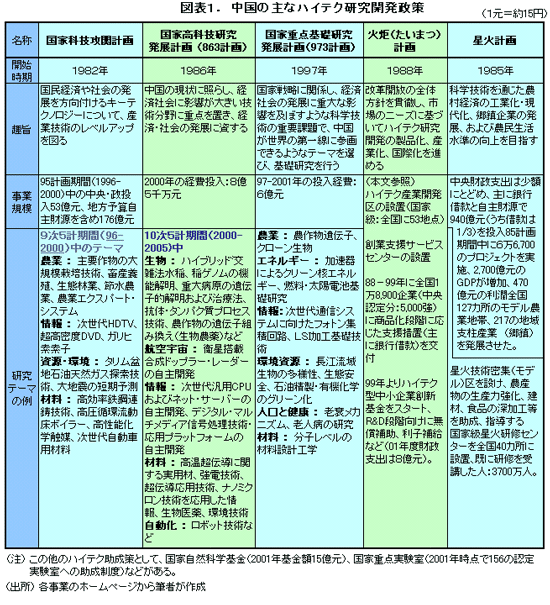
「途上国である我が国はその国情から出発しなければならない。今 後相当長期間にわたって、大量の人力、物力、財力を投入しても 全面かつ大規模なハイテク発展を図る条件は備わらない。世界の 先進国家とハイテク優勢を競って全面競争を展開することは不可 能であるだけでなく、その必要もない。このため、『 863 計画』は 世界のハイテク発展の趨勢(すうせい)と中国のニーズ・実現可能性から出発し、『目標を限定し、重点を突出させる』方針を堅 持し、バイオテクノロジー、航空宇宙技術、情報技術、レーザー 技術、自動化技術、エネルギー技術および新材料技術の7分野の 15 のメーンテーマを選んで我が国ハイテク研究開発の重点とする 。一部のエリート研究者幹部の力量を組織して、今後 15 年の努力により、以下の目標を達成するよう希望する・・・」( 1986 年3 月、トウ小平氏の強い支持の下でスタートした「 863 計画」から)
■シリコンバレー型の産業発展モデルを希求
特にハイテクによる産業発展を強く希求した中国にとって、非常に魅力的に映ったのは米国のシリコンバレー型の産業発展モデルだった。モデルの追求は既に 1980年代に始まった。当時、シリコンバレーでは折からの米国不況のあおりを受けて、留学後現地で仕事をしてきた台湾人技術者が仕事を失い、民主化の兆しが出てきた台湾に大勢戻った。
彼らはそこでシリコンバレーで身につけた仕事のやり方、すなわち大学・研究機関・大手企業でのR &D →インキュベータ(企業ふ化器)、ベンチャー投資機関の力も借りた創業→企業の成長というモデルを利用して次々に事業を立ち上げていった。ここから新竹インダストリアルパークに象徴される台湾ハイテク産業が誕生していったのだ。 80 年代は中国人留学生も米国留学を始めた時期だが、この成功モデルはおそらく彼らにも刺激を与えたに違いない。
■北京・中関村で育ったハイテク企業
同じころ、北京市の中関村地区で中国科学院傘下の研究所、大学をスピンアウトした理系知識人らが「民営色の強い」ハイテク企業を創業、同地に「中関村電子街」が自然成立し始める。四通集団、連想集団など今日の中国ハイテク企業を代表する大企業はここから育っていった。
正統派の国有企業とは明らかに異質な人間が運営するこれらの企業は、当時まだ十分認知されない不安定な存在だったが、ハイテク産業発展を渇望しシリコンバレーの知識も仕入れつつあった中国政府はその存在と可能性に注目し、検討を重ねた結果、 85 年「北京市ハイテク産業開発モデル区」を設置し、その後押しをすることを決めた。
このモデルは早速、深セン市でもまねられ全国に急速に広がっていった。 88 年、政府はさらにモデルのコンセプトを深化させ、以下の3 点セットからなる「火炬(たいまつ)計画」をスタートした。
(1)ハイテク産業開発区の設置
ソフト、ハードの環境を整えたビジネス街または工業団地を造成してハイテク企業を集中的に立地させ、産業発展を加速する。
普通の街中の改革開放進展度、ビジネス環境はまだまだハイテク産業の発展にはそぐわないものだらけだ。
ハイテク開発区は規模の利益だけでなく、遅れたインフラや有害な社会の慣行(例:地方政府の「たかり」的費用徴収)からハイテク企業を守るためのある種「租界」の意味を持っており、対外開放の窓口、経済改革のモデル地区、現代文明建設の基地、実業家の学校など、社会の進歩を願うさまざまな思いが込められている。
北京、深センに続いて、今日では中央が認定した 53 地点のハイテク開発区が全国に設置され、省・市の認定になる開発区はもっと多く設置されている。
(2)創業支援サービスセンターの設置
海外のインキュベーターの経験に学び、各種の起業支援サービスを提供する公益型のサービス機構であり、企業家の育成学校、大学・研究機関と企業を結ぶ連結点でもある。
今日中国全土には 100 以上の創業サービスセンターがある(うち国家認定: 38 )。その性格も分化・多様化し始めており、総合インキュベーター、ソフト・バイオなどの単一業態パーク、大学の創業パーク、帰国留学生創業パークなどに分かれている。そこで設立された企業は 15,500社を数え、従業員は 29 万2 千人。インキュベーターを「卒業」した企業は約 3,900 社あり、うち 32 社が上場を果たしている(数字は 2001 年末)。
(3)助成プロジェクト
ハイテク企業の早期育成のために、新材料、生物技術、電子情報、メカトロニクス、省エネ・新エネおよび環境保全などを重点分野とする助成制度。中央レベルと地方レベルで行われており、 88 年から 99 年にかけて合計1 万9 千近いプロジェクト(うち中央認定: 5,045 )が助成(融資など)を受けた。
R&D のそのものの助成というより開発成果の商品化、産業化に重点が置かれており、ここから北大方正集団の「中・洋文版組システム」、連想集団の「微機系列産品」、巨竜集団、華為集団、大唐集団、中興集団らの「大容量電話局用デジタル交換機」、長春長生公司の「a 干渉素」遺伝子操作制約などの商品が誕生していった。
また、 99 年からはハイテク中小企業育成のために「ハイテク型中小企業技術創新基金」が新たに発足し、R &D 活動についても補助金、利子補給、起業出資などにより支援を始めた。
以上のように、中国のハイテク振興政策は非常にダイナミックだ。インキュベータの設置、若年層における「創業」モデルの浸透などは目を瞠るものがあり、まさに“カエル跳び”型進化が達成されつつある。
■国際的ハイテク企業の出現はいまだに
他方、問題も数多い。技術レベルの低さは言うまでもない。上述のハイテク型中小企業技術創新基金では実施プロジェクトの3 割が特許などの知的財産権取得につながったものの、特許を取っても売れる商品に育つほどのパワーのあるものはまだまだ限られる。
まして国際的に通用するレベルとなるとなおさらだ。中国には往時のソニー、ホンダのような技術的にユニークで国際的に通用するような新興ハイテク企業はまだ出現していない。しかし、それは当然予想されることだ。それ以外に「カエル跳び」型進化の難しいと思われる課題を3点挙げたい。
■企業への資金供給チャネルが未発達
第1はハイテク産業化の各段階に必要な資金供給チャネルが不十分なことだ。スタートアップ段階の資金的助成には一定の充実が図られたが、商品化(中国では「中間試験」という)や企業としての規模拡大には直接資本市場および間接金融両面からのサポートが欠かせない。ところが、メーンボードに上場できるほどの大企業に育てば資金調達面の不自由はなくなるが、スタートアップからそこに至るまでの途中の資金調達ルートが「中抜け」している。
■延期されたベンチャー株式市場創設
直接資本市場については、中国でも数年前までのIT (情報技術)バブル期には国内外から大量のリスク投資がIT 関連企業に流れ込んだ。しかし、決定的な弱点はベンチャー株式市場がなく、投下資本退出のメカニズムが備わっていないことだ。2 年ほど前、「創業板」(セカンドボード)の設立認可間近の観測が流れたが、その後の世界的な株価下落、中国メーンボードの運営レベルの低さ、同様のベンチャー市場を開設している香港への配慮などにより延期されたままである。
開設が早晩成るとしても、それまでは香港、ナスダック(米店頭株式市場)の海外市場に上場するか、相対のM &A (企業の合併・買収)で売却するしか投下資本退出の道がない。海外で通用する企業は非常に限られるし、相対売買は不確実で情実・不正がつきまとう。創業市場が開設されれば理論的には問題が解決するが、創業市場が本来のパフォーマンスを発揮するにはこれまた証券市場全体の成熟を待つ必要がある。
■中小企業への融資能力に乏しい金融機関
資本市場の整備では日本も人のことが言えた義理ではないが、日本にはまだ間接金融がある。なかでも中小企業金融は日本が誇ってもよい分野だ。ところが、中国はここでも深刻な問題を抱えているのだ。全国預金残高の7割以上を占める4 大国有銀行は大型国有企業向けの存在で中小企業融資がなかなかできない。かつての都市信用合作社といった小口金融機関が商業銀行に転進してこの分野を受け持とうとしているが、融資能力がつくには時間が必要だ。
政府はいま中小企業の振興のための重点施策として「中小企業信用担保制度」の普及に努めている。日本の信用保険に類似した制度で、既にこの2 年あまりの間に全国各地で 400 以上の担保基金が設立された。しかし、驚くのはその運用倍率(基金額の何倍までの融資残を許容するか)の低さだ。運用実績、特に事故率のデータなどが乏しいので「慣らし運転」をせざるを得ず、せいぜい 10 倍以内、これでは基金を造成するのもたいへんだ。
■知財権侵害では中国企業も被害者に
第2として知財権の保護を挙げたい。中国が抱える問題として言い古されたが、その重要さはなお強調して余りある。知財権侵害の被害は決して外資・外国企業だけが被っているわけではない。以前はマオタイ酒のような名産品を除けば、中国企業が保護すべき知財権というものを持っていなかったが、今日では特許にせよ、ソフトウエア著作権にせよ、中国企業が被害者になるのが日常茶飯化しつつある。
体力があり、その気にさえなれば相当な対抗手段がとれる外国の大企業と異なり、資金も乏しい中国のハイテク中小企業がその成果の技術を侵害されればやっていけなくなるのは必定だ。中国政府も近時ようやく知財権保護に本腰を入れ始めた。その理由はまさに、侵害したい放題のままでは民族ハイテク産業が育たないことに気付いたからだ。
■起業に走るも下請け仕事は敬遠
第3に合理的な商慣行の未発達を挙げたい。その典型はソフトウエア開発業に見られる。「鶏頭牛後」をモットーとする中国人はみんな「老板」(社長)になりたがる。ソフトは元手もかからないため、特に起業志願が集中する。北京中関村などはソフト開発会社だらけだ。みんな何の仕事をしているのだろうと思ってきいてみると、けっこう自社ソフトを開発しているという。それは立派だが、よく聞くと実力の伴わない会社が「自社製品」を出すものだから、質は非常に悪いという。
日本では中小のソフト会社は大手が元請けで取ったシステム開発の下請けをするのが普通だ。企業の成育期には合理的な選択だ。中国でも下請けはもちろんやっているだろうが、どうも影が薄く、やりたがられない仕事の印象がある。理由は元請けの下請け搾取(劣悪な代金支払い条件など)、あるいは力のついていない下請け側も納期・品質などの要求を満たせないからだ。
そうと分かって、改めて思ったことがある。日本でも合理的、公平な下請け慣行の形成は永く中小企業政策の難題の1つだった。ソフトに限らない、建設、流通(大手小売りの納入業者いじめ)などさまざまな業種で搾取的な商慣行がはびこり、「下請代金支払遅延防止法」に代表される施策が講じられてきた。筆者の経験では百貨店・スーパー業界の納入業者への支払いについて手形のサイトを百何十日もの長いものにしてはならないといった行政指導があった。
※「下請代金支払遅延防止法」は固有名詞です
■「カエル跳び」だけでは中国を変えられない
こういう商慣行は「世の現実」そのものであり、社会全体の成熟・進化、「民度」の底上げがあってはじめて改善されていくものだ。
こうしてみると、中国経済が抱える大きな課題が見えてくる。中国ほど「ピンとキリ」の格差が大きい国も珍しい。ピンには我々日本人が刮目し居住まいを正して接すべき素晴らしいものがある一方、キリには目・耳を疑うようなお寒い現実がある。先に「ハイテク開発区は有害な外界からハイテク企業を護るための『租界』だ」と述べた。80年代にトウ小平が始めた「特区」にもこれに似た一面があり、中国独特の流儀といってよい。ハイテク開発区ではインキュベーターの設置や若年層における「創業」モデルの浸透など狙いどおりの長足の進歩が達成される。ピンが構想し、ピンが呼応して実現した“カエル跳び”だ。
しかし、やがては企業が「租界」から外界に出ていく段階、更には「租界」を解いてキリの現実を変えなければならない段階に至る。証券市場の運営レベルの向上、中小企業金融の普及、合理的な商慣行の発達などは大勢のキリが絡む事柄だけに、すべて時間のかかる課題ばかりだ。つまり、中国にはその遅れをステップ・バイ・ステップで縮めなければならない課題がまだまだあるということだ。
■中国に根付くか日本の商慣行
中国人はよく日本から学びたいこととして「管理(マネジメント)」を挙げる。「日本こそコーポレートガバナンス(企業統治)に問題を抱えている」という意識のある我々は、その度に居心地の悪い思いをする。しかし、考えてみると、「イントラ(社内)」でなく「インター(企業間)」については、日本の商慣行は「信頼」を基調とする分業のプラットフォームとして悪くないものを持っている(問題がないとは言わないが、「よりマシ」だ)。
いま、日本のソフト業界の中国への外注が急速な勢いで進んでいるが、これで「よりマシ」な商慣行が中国業界に根付けば、お互いに得ができるというものではないか。
■ハイテク政策の重心、基礎研究へ
さて、冒頭で中国の技術開発政策は産業化、応用に重点を置いていると述べたが、経済発展につれて、中国でも次第にハイテク政策の重心が基礎研究に移りつつある。
「 ・・・現有の基礎研究事業配置の基礎に立って、国家戦略目標 を取り巻き、経済社会発展に重要な影響を及ぼすような、かつ、中国が世界の一席を占めることができる重点分野において、優秀な科学者が科学の前縁と重大な科学問題に狙いを定め、重点基礎研究を展開する・・・」( 1997 年に制定された「国家重点基礎研究 973計 画」より)。
前掲 863 計画がだいぶ「うつむいた」感があったのに対して、 その10年後に制定された973 計画の趣意はすこし「顔を上げ」ているではないか。
■米国での特許取得件数では日本と大きな差
もちろん、物事の順序から言っても、基礎研究は応用開発よりもさらに課題が多い。いま、中国でも「ナノ・テク」が大流行だ(ナノ・ミクロンを中国流に縮めて「納米( nami )」技術という)。あちこちの研究機関が取り組み始めている。
しかし、「中国でも最先端の技術を研究している」だけではとうてい不十分だ。世界に先駆けて技術を開発し、その特許を押さえなければ本当の意味で基礎研究の成果が上がったことにはならない。
図表2 は研究開発の成果を「モノにしたか否か」を示す国別の米国特許取得数だ。日本は 98 年で 28,259 件と諸外国の中でダントツの1位、これに対して中国は、数は増加してはいるものの、同年で 110 件と、日本と比べるとまだ大人と子供以上の格差がある。
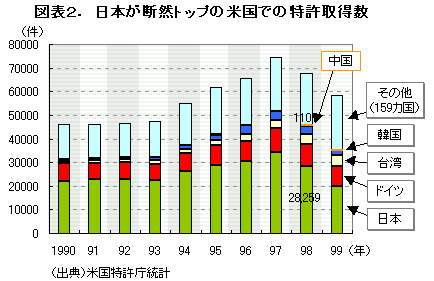
■論文引用件数で健闘し始めた中国
他方、図表3 は各国研究者の発表した論文がどれだけ第三者から「引用」されたか、つまり、その論文がその道で有する値打ちのほどを学術領域別・国別に示す指標だ。ここでは日米中と東アジアの国・地域を参考に挙げてみた。特許までたどりつけなくても、こちらでは予想以上に中国が健闘している。特に材料や化学、エンジニアリングなどの領域では既にバカにならないレベルだ。
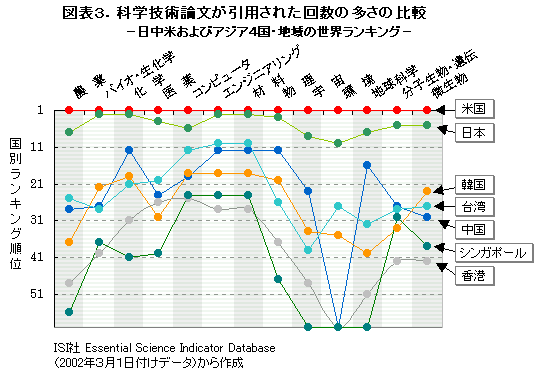
■基礎研究でもやがて追い付く
昔、日本も「猿まねの日本」と言われ、基礎研究でおよそ世界に貢献できなかった時期が続いた。その日本人にできたのだ。多少時間がかかったとしても、いま日本の学生の何倍も勉強している中国人が基礎研究で追い付いてくることは間違いないと思われる。
特に、中国が輩出した最良の理系人材の多くが留学・就職でいまは米国にいる。中国の才能の一定部分は米国発の特許や論文にカウントされているのだ(米国という国の競争力の所以)。昔はまず帰国しなかった彼らが最近は帰国し始めていることも頭に置いておく必要がある。
基礎研究分野における中国のキャッチアップの速さはどれくらいだろうか。カエル跳びか、ステップ・バイ・ステップか、それともその中間か。当然ながら、その速さは我々日本の歩みの速さによっても違って見えてくる。
