| 日中企業の提携関係は、双方の企業がお互いの強みを生かしあう「強みのトレード」と、日本企業が中国企業の中核部分に出資する「本丸への資本参加」という新段階に達しつつある。 | |
| 「本丸への資本参加」は、日中企業の新たな同盟関係の構築、および会社の分割・売却やM&A(合併・買収)への慣れなど中国経済内部で起きている変化の象徴という点で注目される。 | |
| こうした変化はWTO(世界貿易機関)加盟を果たした中国産業界の生き残りに向けた強い危機感の現れであり、「中国経済脅威論」が盛んだった1年前とは様変わりの状況になっている。 |

1年前の日中経済関係を思い返すと、「労賃と人民元が安すぎる」を合言葉とした中国経済脅威論が猛威を振るっていた。日本経済に危機感を持つのはよいが、その処方に何ら示唆を与えないあら探しのような論調を聞いて「日本もそこまでヤキが回ったか」と暗然たる思いがした。
■中国経済脅威論から1年後の変化
あれから1年、産業空洞化など日本経済の将来に対する憂慮は変わるところはないものの、「それを言っていても始まらない」と、行動を起こす企業が増えて、少し様子が変わってきたように感ずるのだ。
別に対中投資ブームが再来したことをはやすつもりはない。今年に入ってから上海など中国沿海部の一部の都市で日本の対中投資が香港を抜いて国・地域別投資額ランキングのトップに立った。専門サイトの対中進出案件のクリップを見ると、まさに目白押しの様相を示している。しかし、北京や上海の商社筋などでは、「またぞろ、『バスに乗り遅れるな』式、事前調査や詰めの甘い進出案件が増えてきた感じがあって不安」といったぼやきも聞かれるのだ。1990年代にあれだけ懲りたはずなのに。
■従来と異なる日中提携の行動様式
様子が違ってきたと感ずるのは、従来と異なる行動様式に立った日中企業の提携が生まれ始めているからだ。第1の類型は日中双方の企業による「強みのトレード」が明確に出た提携だ。中国企業との合弁・提携は、対外開放で独資(100%日本側出資)企業の設立が広く認められるようになるにつれて廃れた。経営方針を巡る中国側出資者との対立や調整の手間を嫌気してのことだ。
確かに製造、特に自社販路を使った輸出を念頭に置くメーカーにとっては、「中国側は口を出さずに任せて欲しい」というのが本音だ。政府当局との渉外事務も自社でこなせる経験を持った企業なら、わざわざ合弁を選択して「苦労を背負いにいく」必要はない。
■中国企業の「強み」生かす日本企業
しかし、ことが製品の国内販売やアフターセールスになった途端、事情が変わってくる。各地で信用のある代理店を選定し、全国販売網を構築するといった作業では、外資企業は中国企業に到底かなわない。特に企業幹部の現地化が下手な日本企業はなおさらだ。
中国はWTO加盟に伴い、3年以内に外資100%企業に輸入品を含む国内流通を認めることが義務付けられている。しかし、早くから中国に参入して経験も豊富な企業がそれを承知の上で、優秀な中国企業が持つ販売・アフターセールス網に高品質の自社製品を流してもらおうとしている。これは中国企業の「強み」を活用する立派な戦略決定だと言える。
この類型に分類される最近の日中提携例として、ホンダとオートバイメーカー、海南新大洲摩托車による合弁、三洋電機と家電の海爾(ハイアール)による合弁、まだ交渉中だが松下電器産業と家電のTCLによる合弁が挙げられる(図表)。
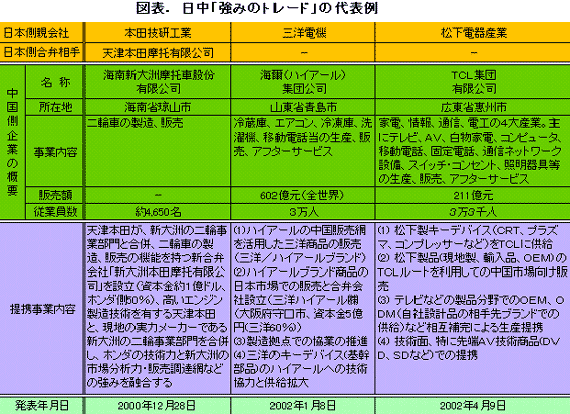
■「販売拠点」と「技術」を互いに確保
ホンダの例では従来のホンダ系列店750店舗に加えて海南新大洲の系列店3,500店舗が、三洋電機の例では海爾の直轄販売会社42社、販売取扱店9,000拠点、サービス拠点11,900拠点が、松下電器の例では、TCLの家電販売部門だけに限っても直轄販社33社、177営業所がそれぞれ利用可能になる。
自社製品の中国販路拡大に加えて、3社が生産する基幹部品を相手方の製造部門に供給することを合意したことも、日本企業が強い部品の安定的販路の確保という点でメリットに数えられる。
中国側企業が3社に見出した「強み」やメリットは、ずばり日本の技術だ。各社発表を見ると、ホンダはエンジン技術を、三洋電機は電池、液晶、モーター技術を、松下電器はDVD(デジタル多用途ディスク)など先端AV(音響・映像)製品技術を挙げている。
■中国企業の日本市場進出も
技術に加えて、三洋電機の場合は海外進出に力を注ぐハイアール・ブランド製品のために、日本国内の商流・物流・アフターセールス網を利用させるとしている。松下電器もOEM(相手先ブランドによる生産)形態ながらTCL製品の販売を、ホンダは当初発表にはないが生産が軌道に乗れば低価格製品をOEMで受け入れる可能性はある。
これから海外進出しなければならない中国企業にとって、日本のマーケットパワーも買える点も、もう1つの材料だ。
■外国資本に「本丸」への出資許す
第2の類型は、「資本」を1つのキーワードにした合弁だ。まだ「気配」にとどまるが、今後中国側企業への資本参加を組み込んだ新しいビジネスモデルの合弁が増える兆しがあるのだ。
従来型の合弁は新事業を行う「出城」への出資だったのに対して、新しい出資形態は中国側の「本丸」への資本参加だという差異がある。国有企業にせよ、私営企業にせよ、5年前は外国資本に「本丸」を触らせようとはしなかった。大きな意識変化が起きていると言えよう。
この類型は、まだ第1の類型ほど鮮明ではない。ホンダの事例は合弁会社の新規設立だから、「出城」への出資型に見えるが、海南新大洲の事業のコア(海南島の製造部門)が新会社に供出されていることから、本質的には「本丸への資本参加」どころか、ホンダによるM&A(合併・買収)といってよい。
三洋電機の事例にはこの「資本」の要素がないものの、松下電器は4月の意向書締結の発表時にはなかったが、現在、資本参加も含めて詰めを行っていると報じられている。
■技術供与と資本参加で同盟関係築く
このような資本参加に注目すべき理由は2つある。第1は、将来台頭が予想される中国企業とのアライアンス(同盟関係)構築を意味するからだ。資本参加の比率が高まれば、相手企業の成長によるキャピタルゲインの獲得にもつながる。
このことは日本企業の虎の子の資産である技術を供与する際の重要な前提になる。最低でも、技術を得て発展する企業は盟友だという安心感が生まれるし、それがポートフォリオ投資的な色彩を帯びれば、技術供与の収益性を高めることにつながるからだ。
筆者はかねて技術供与と資本参加の組み合わせが日中企業の相互補完を加速するはずだと述べてきた( 2000年7月4日および同年8月31日付当コラム参照)。ポートフォリオ投資というと、すぐIT(情報技術)やベンチャー企業を連想するが、機械その他の伝統産業分野でも、プライベートエクイティー投資と技術供与を組み合わせれば、ミドルリスク・ミドルリターンの投資案件を形成することは十分可能だ。上述の事例はまだ明確ではないが、そういう方向に発展する兆しも感じられる。
■中国の変化象徴するトヨタの仕掛け
資本参加に注目する第2の理由は、それがいま中国経済で起きている変化を象徴するからだ。その意味でもう1つ、日本企業が水面下でからんだ興味深い事例がある。トヨタ自動車の中国事業の主力拠点になる天津汽車シャレード部門が中国有数の自動車メーカー、第一汽車(長春市)に吸収合併されることだ。
トヨタはこの合併劇の影の仕掛け人だ。シャレード部門の親会社、天津汽車は適正規模を数倍上回る過剰人員と売れば売るほど赤字がたまる財務体質のせいで、本格市場参入を期するトヨタの中国パートナーたる資格を持ち合わせていなかった。
第一汽車に高級車種を含むトヨタとの同盟関係を提供する代わりに、シャレード部門を健全企業として切り出して天津から買収してもらう――。中国自動車業界で春からうわさとしてささやかれてきた構想が6月14日、北京オートショーにおける第一汽車と天津汽車の共同発表でベールを脱いだ。
■会社分割・売却・M&Aになじみだした中国企業
トヨタは公式発表をしていないが、以来中国の経済メディアはこの話で持ちきりだ。従業員数万人を擁するような特大国有企業同士、しかも「おらが企業」意識(地方保護主義)がことさらに強い自動車業界で、天津と長春という遠く離れた都市の企業同士のM&Aが実現したことは中国でも驚きの念をもって迎えられている。
中国の産業界は、会社の分割・売却やM&Aといった考え方に急速になじみつつある。日本企業はこの点に注目してほしい。今後中国市場で事業を展開するときに欠かせないツールになるからだ。
■危機感が新しいモデルの推進役に
日中企業の「強みのトレード」といい、大胆なM&Aといい、こうした変化が中国で起こる背景は何か。「危機感」の一言だと思う。中国では、家電業界でも自動車業界でも存亡をかけた競争が繰り広げられている。業界のトップ企業ですら、勝ち抜くための武器をいま手に入れなければ数年先が危うい、という危機感に駆られている。「本丸」に外国出資を受け入れる決断をしようとしているのもそのためだ。
WTO加盟を果たし、いよいよグローバリゼーションの大海に本格的にこぎ出そうとする中国企業が技術の強みを持つ日本企業との戦略的提携を模索しようとしている。日本企業も昨年の「中国経済脅威論」の総括のうえに、この声に呼応しようとしている。みんなが成功するという保証は全くないが、脅威論から1年、面白い成り行きになってきたではないか。
