中国経済の台頭や相次ぐ生産拠点の海外移転の動きを見て、日本国内では、産業空洞化の一層の危機、果ては中国経済脅威論が語られるようになった。
日本経済の現状に危機感を持つことは必要だが、一部の論調を見ていると、事実に基づかないパーセプションが一人歩きしている感もある。その最たるものが、相次ぐ中国への生産移転(空洞化)→輸入急増→貿易黒字急減へ、という「分かりやすい」見方だ。
今年度上期の日本の貿易黒字は、約210億ドル(1$:120円換算)、43.3%の急減を示した。このうち、対中貿易は輸出が157億ドル、輸入が291億ドル、差し引き133億ドル。これは日本が抱える最大の二国間赤字であり、赤字幅も前年同期比24.4%と大幅に増大した。それだけ見ると、確かに、人を驚かせた貿易黒字幅の急減には中国が大きく関わっているように見える。
しかし、貿易黒字幅の急減は、むしろ世界経済全体の動きと密接に関わっている。輸出の減少については、電気機器の減少、輸入の増大については中国が得意な繊維類と「その他」類の増大が顕著だが、鉱物性燃料の増大(油価の高騰)はそれを上回る。つまり、貿易黒字の急減はIT不況と油価の高騰による面が相当大きいということだ。
相手国別に黒字幅減少への寄与度を見ても、西欧全体で24.3%、台湾が17.6%、中国12.4%、アメリカ9.9%、シンガポール9.1%と続く。必ずしも中国が他を圧して日本の黒字を減少させている訳ではない。
対中輸入が絶対額でも、増加幅でも他を圧して大きいのに、中国の黒字減少への寄与がそれほど大きくない理由は明らかである。対中輸出も伸びているからだ。今年度上半期の対中輸出は19億ドルで、前期比では14.1%伸びた。1−6月(暦年上半期)だけを見れば、実に35億ドル、29.2%の伸びだ。軒並み急減少する各国向け輸出の中で、対中輸出だけが気を吐いているのだ。
そうはいっても、もともと金額にすると輸出の2倍近い対中輸入の伸びが18.5%と、輸出の伸び14.1%をかなり上回っているため、対中貿易赤字は増大する一方だとの反論があるだろう。(表1参照 [![]() PDF:13KB] )
PDF:13KB] )
しかし、図2を見てほしい。
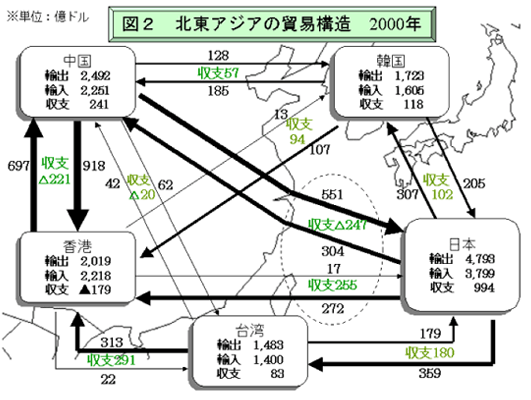
2000年の日本の通関統計上、対中貿易赤字は確かに247億ドルに達しているが、傍らで対香港の貿易黒字はこれを上回る255億ドルに達している。・・・香港相手に255億ドルの黒字? こんなことがおきる理由は統計の方法にある。輸入統計を集計するときは、原産国がチェックされる。たとえ輸入貨物が香港から運ばれてきても、中国原産と判断されるものは対中輸入に計上される。しかし、香港に向けて輸出された貨物がその後どこに再輸出されるのか・・・? 通関統計はそこまで追跡しない。周知の通り、香港は対中輸出の大中継地だ。大量の貨物が香港経由で中国に再輸出されているが、その数字は対中輸出には計上されない。
他国の統計も同じだろうが、通関統計にこのような不対称性があることは、注意すべきだ。香港の貿易統計を見ると、日本から香港経由で中国へ向かう再輸出は134億ドルだ(2000年)。この数字を前提とするなら、正味の対中貿易赤字は113億ドル、すなわちア首連・サウディ並み、豪州の2倍程度ということになる。
図2では韓国、台湾にも注目してほしい。両者は日本から大量の部品原材料や機械類を輸入するため、いずれも対日貿易赤字が大きい。一方、両者とも対中+対香港の貿易収支は大幅な黒字を記録している。
つまり、日本、韓国・台湾、中国(香港を含む)の間には、貿易収支のグー・チョキ・パーとも呼べる相互補完的な構造が存在しているのだ。確たる推計はできないが、品目別の内訳を見ると、日本から輸出された部品・原材料が製品に組み込まれて中国に輸出されていることは容易に推測できる。つまり、日本から中国への間接的な再輸出だ。
以上、全体を通して分かることは「中国への産業移転・空洞化が輸入急増を招き、貿易黒字を急減させている」といったパーセプションは事実と符合しないということだ。
近隣に中国のような高成長且つ手強いライバルがいることは決して悪いことではない。グー・チョキ・パーの北東アジア地域で中国が大きく成長したことは確実に地域全体の成長を促したはずだ。中国の成長がなければ、過去10年間の日本経済はもっと低迷していたかも知れない。
しかし、それはもちろん同時に日本を厳しい競争に直面させることでもある。80年代、日本車から厳しい競争を挑まれた米ビッグ・スリーの有様を描写した"Rude Awakening"(安眠から乱暴に揺り起こされた)という本があったと記憶する。
いままさに同じような立場に日中両国が立とうとしている。中国の挑戦を受けて、日本企業が効率と競争力を復活させられるかどうかは我々次第だ。しかし、中国好調の原因を人件費の安さや人民元の交換レートに単純に求めて不平を鳴らしているようでは、勝負の結果は見えたも同然といわざるを得ないだろう。
